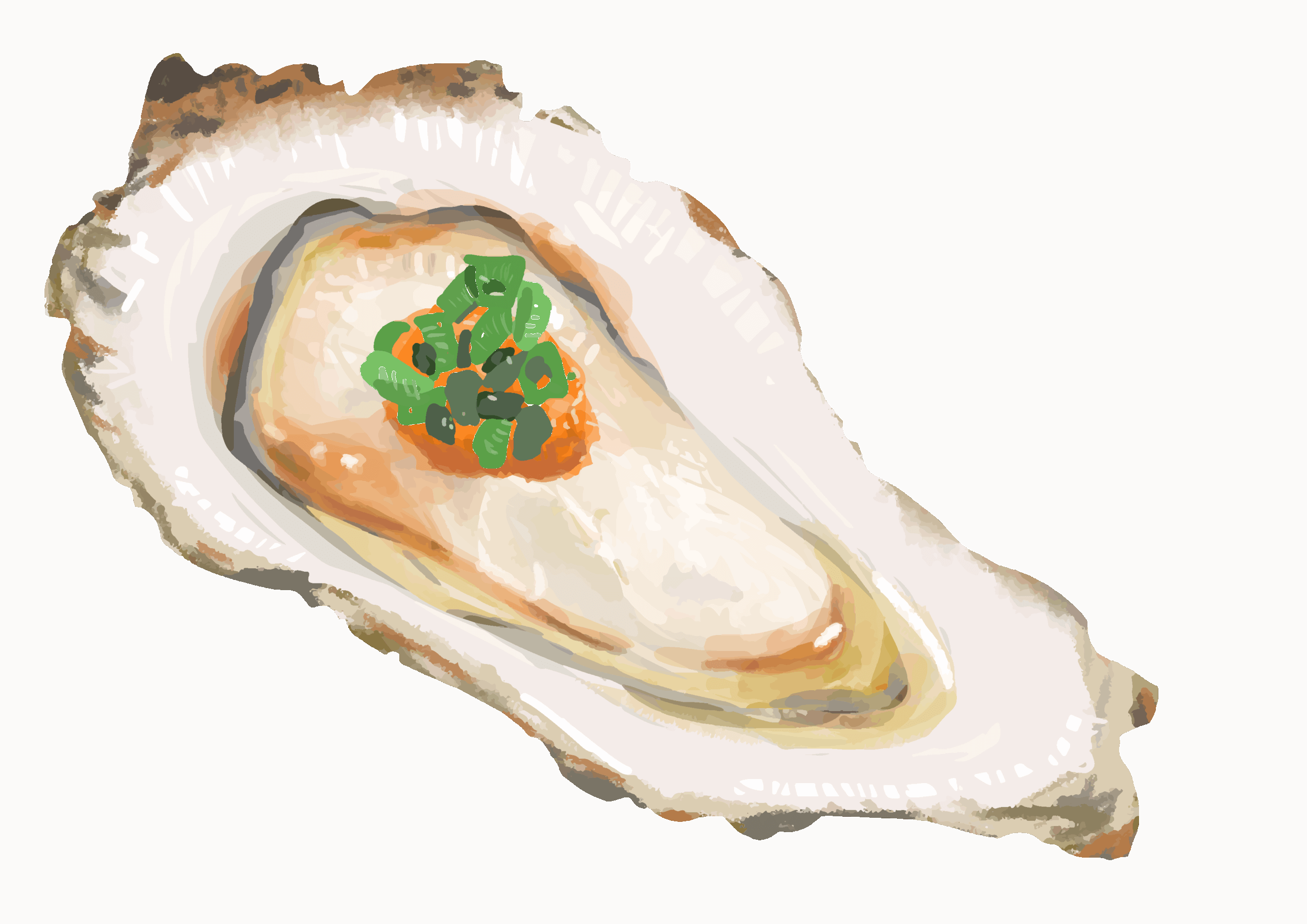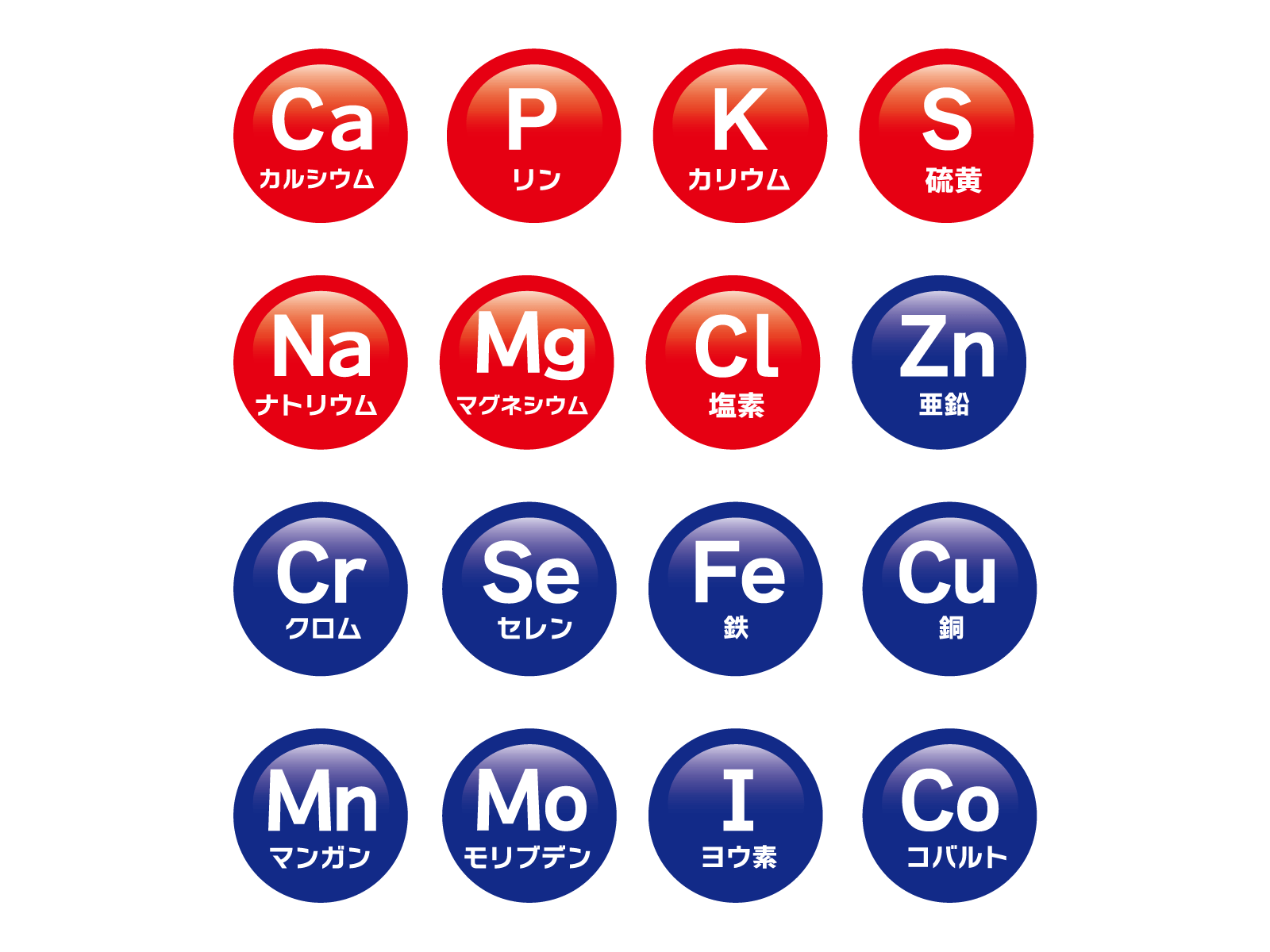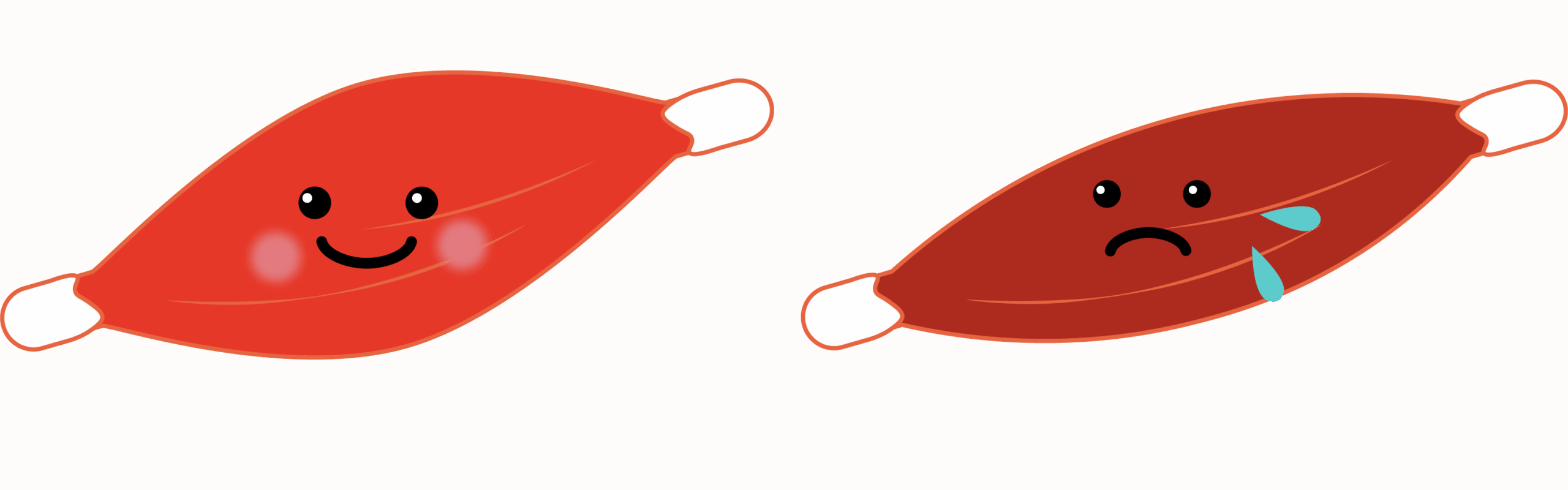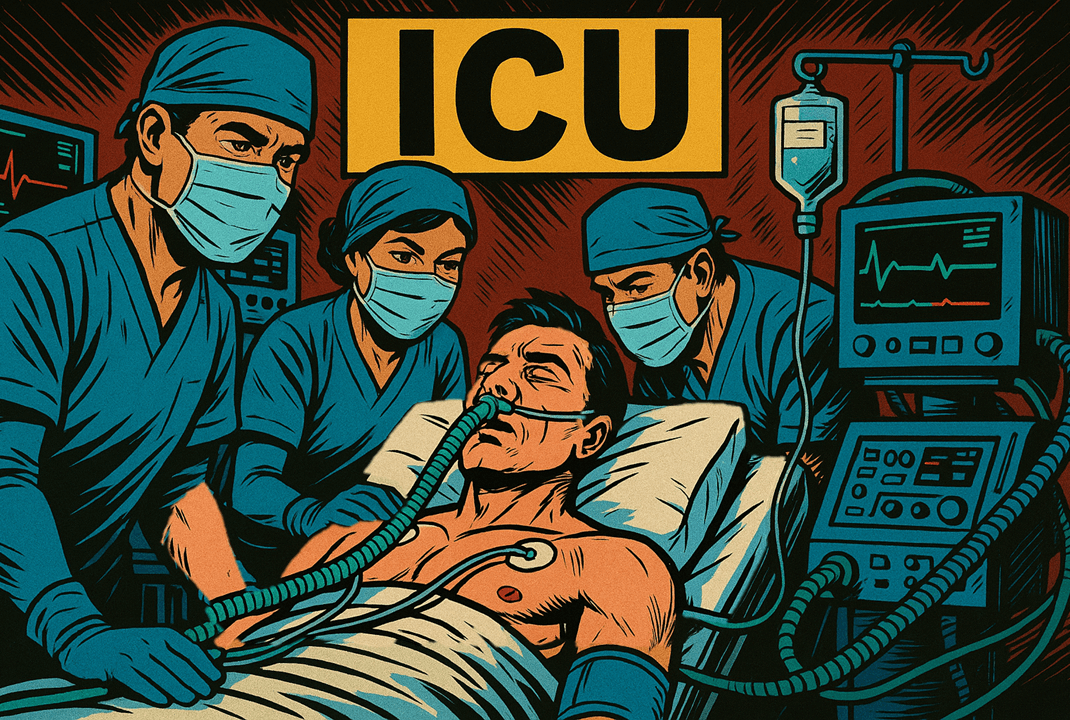Ns.やちくん
Ns.やちくん近年、栄養に関する学会界隈では、筋肉量が予後に最も重要との認識が高まっており、種々の測定方法、判定基準が紹介されていますが、保険診療上はこの重要性に見合った算定はなされているのでしょうか。調べてみました。
2025年現在の筋肉量測定と診療報酬
2025年現在の保険診療では筋肉量測定を算定できない?
現時点では残念ながら、「筋肉量測定」自体を単独の行為として診療報酬上の項目として算定する設定は、日本の診療報酬制度には無い模様です。
「診療報酬が算定できないので、やらない」という考えは残念なのですが、算定のない検査を「積極的に行いましょう!」と皆の衆に言い難いのは事実です。診療の人的体制が超余裕なら良いのですが…。日常の診療を安全確実に行うために、経営面にも配慮しながら人員を適切に配置・投入することのほうが、ボランティア的な検査を行うことよりも、現状は優先されると思われます。
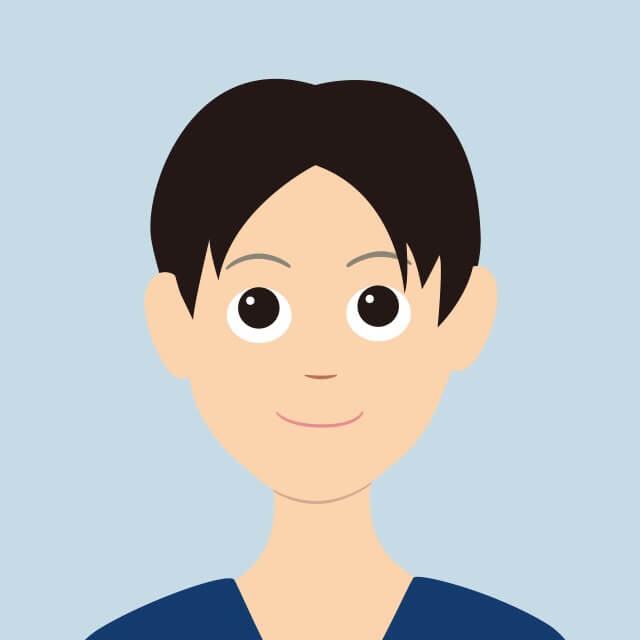
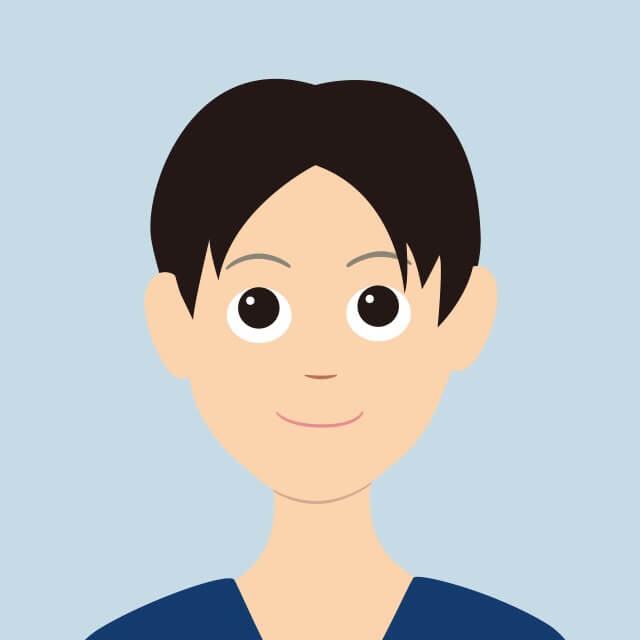
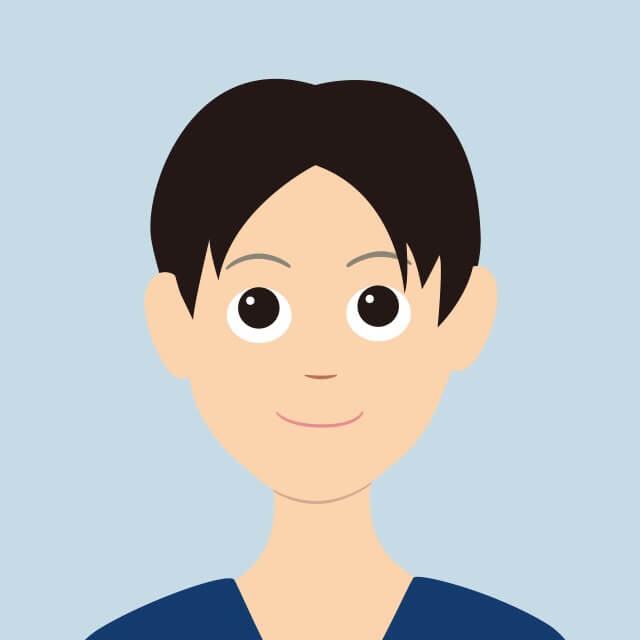
当院の回復期リハビリテーション病棟では、BIA法による筋肉量測定を行っていますが、この費用は、回復期リハビリテーション病棟の入院料に基本的に包括されていると考えています。
2024年度の診療報酬改定で、回復期リハビリテーション病棟ではGLIM基準を用いた栄養評価の実施が必須となりました。これは、入院患者さんの低栄養状態を早期に発見し、適切に対応するためです。GLIM基準による評価を実施するにあたり、筋肉量測定(機器の使用を推奨、代替として身体計測も可)が必須になっておりますが、回復期リハビリテーション病棟運営上、当然行うべき管理業務の一部と見なされます。このため、その実施にかかる費用(機器代、人件費、維持費など)は、別途点数を算定するのではなく、入院料の点数の中に含まれていると解釈されます。測定を行っているスタッフには感謝の念が堪えません。
労力を診療報酬にどうしても関連付けたい場合は?
ボランティア精神で筋肉量を測定するのではなく、診療報酬にも関連付けたい場合は、「保険請求できる病名で体組成を測定できる検査を行ったついでに筋肉量も測定する」のが正攻法ではないでしょうか。具体的には、3つのパターンがありえます。
上記以外の場合、例えば健康診断、スポーツジムでの利用、美容目的などは、保険診療上の算定項目に付随しない目的であるため、原則として自由診療になります。
BIA法、DXA法の対象疾患
筋肉量を診療の一環で測定するには、保険請求できる病名でBIA法による体水分量測定を行う際や、保険請求できる病名でDXA法による骨密度測定を行う際のいずれかで、付随する項目として行うのが現実的と思われました。
BIA法を用いた体液量等測定:D207 60点(2024年度)
「体液量等測定」の算定対象となるのは、主に体液管理が予後や治療効果に直結する重篤な疾患です。
- 慢性腎臓病(CKD):透析導入前後、および透析中の患者の体液過剰(浮腫)やドライウェイトの設定のため。
- 心不全:体液貯留(うっ血)の状態評価や、利尿薬などの治療効果判定のため。
- 肝硬変:腹水や浮腫の管理のため。
- 重度の低栄養状態:サルコペニアや低アルブミン血症を伴う疾患(例:悪性腫瘍、消化器疾患)の栄養管理のため。
BIA法を用いた「D207 体液量等測定」の算定回数は、原則として「一連につき」とされており、特定の期間の制限はありません。この検査は、主に腎不全や心不全など、厳密な体液管理が必要な患者に対して、治療方針の決定や変更のために行われますが、患者の病態が安定し、治療上の管理が必要でなくなった場合は、頻回の測定は算定できないことになります。医学的な必要性に基づいて、適切な頻度で実施する必要があります。
DXA法を用いた骨塩定量検査:D217 450点(2024年度)
骨塩定量検査は、骨粗鬆症の診断およびその経過観察の際のみ算定可能です。原則として4か月に1回を限度とします。その他副甲状腺機能亢進症など、骨代謝に影響を及ぼす特定の疾患も適用となりえます。
- 腰椎撮影:D217 骨塩定量検査 1 360点
- 大腿骨同時撮影:大腿骨同時撮影加算 90点 同一日に腰椎撮影と大腿骨撮影を行った場合に、360点に加算されます。
➡360+90=450点



当院ではどんな患者さんを対象に、誰がどのような方法で行い評価するか、評価の結果どんな介入がありうるか、考えてみたいです。個人的には、筋肉量が減少していても挽回のチャンスがある、プレフレイルの患者さんや術前患者さんに対する測定に、診療報酬が算定できるようになってほしいです。
まとめ
- 「筋肉量測定」自体は2025年現在、単独の行為として診療報酬を算定できません。
- 回復期リハビリテーション病棟では、GLIM基準を用いた低栄養診断が必須化されたため、必ず筋肉量を評価しますが、これらの行為は回復期リハビリテーション病棟入院料に包括されています。
- 筋肉量測定を診療報酬に関連付けたい場合は、体水分量測定の対象疾患にBIA法を用いる場合や、骨密度測定の対象疾患にDXA法を用いる場合に、ついでに筋肉量測定を行うのが現実的と思われます。